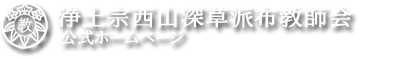【担 当】 大脇光寛 師 〔京都市中京区 光明寺 住職〕
【御 題】 「お盆」
【御 題】 「お盆」
お盆は、ウランバナというインドの言葉です。孟蘭盆を音写したものです。救倒懸といい「逆さに吊るされるほどの餓鬼の苦しみから教う」と言う意味があるのです。
「孟蘭盆経」というお経に説かれている話によると…。お釈迦様のお弟子のなか、もっとも神通力に優れていたという目連尊者。彼がその神通力で亡き母を見てみると…なんと、あろうことか餓鬼の世界に堕ちていたのです。あわててお釈迦さまにこれを告げ、母親を教う手立てをうかがいました。お釈迦さまいわく「雨季の修行を終えた僧侶たちに食べ物を供養すれば、その功徳によって汝の母は教われ、汝自身も大きな功徳を得るであろう」と。教えていただき、そのとおりにすると、たちまちに母親は餓鬼道から逃れたということです。
目連尊者の母親は、我が子可愛さのあまり他人を思いやる心を見失い、餓鬼道に堕ちました。孟蘭盆経は私たちに、自分の身内ばかりのことではなく、むしろ他人を慈しむことの大切さを説いてます。そして、何も目連尊者の母親だけの話ではありません。私たちも自己中心的な生活でいつも怒り、貪り、愚痴って、逆さまの苦しみの中に日々を送っております。人間の持つ悲しき業というのでしょうか。この業から解き放たれることのできるのがお盆なのです。
そして、いずれはご先祖の列に加わる私たちです。ですから、お盆はなつかしい心の故郷とも言えるのです。
宗教詩人 坂村真民さんの「お盆」という詩を読ませていただきます。
亡くなった人たちに会える日をつくって下さった
釈迦牟尼世尊に 心からお礼を中し上げよう
そして亡くなった人たちが 喜んで来て下さる 楽しいお盆にしよう
せっかく来て下さった方々を 悲しませたり 落胆させたり
もう来ないことにしようなど 思わせたりしない
心あたたかいお盆にしよう
迎え火のうれしさ 送り火のさびしさ
そうゆう人間、本然の心にかえって
守られて生きる ありがたさを知ろう
と、念唱されました。
お盆には、ご先祖を思い、亡くなった人たちをしのびながら、ご縁ある我が身を実感し。
お陰さまの心、供養の心をもって、餓鬼道に堕ちぬ自分を作ってゆきましょう。
ご先祖様はそうした子孫を見守ってくださることでありましょう。
「孟蘭盆経」というお経に説かれている話によると…。お釈迦様のお弟子のなか、もっとも神通力に優れていたという目連尊者。彼がその神通力で亡き母を見てみると…なんと、あろうことか餓鬼の世界に堕ちていたのです。あわててお釈迦さまにこれを告げ、母親を教う手立てをうかがいました。お釈迦さまいわく「雨季の修行を終えた僧侶たちに食べ物を供養すれば、その功徳によって汝の母は教われ、汝自身も大きな功徳を得るであろう」と。教えていただき、そのとおりにすると、たちまちに母親は餓鬼道から逃れたということです。
目連尊者の母親は、我が子可愛さのあまり他人を思いやる心を見失い、餓鬼道に堕ちました。孟蘭盆経は私たちに、自分の身内ばかりのことではなく、むしろ他人を慈しむことの大切さを説いてます。そして、何も目連尊者の母親だけの話ではありません。私たちも自己中心的な生活でいつも怒り、貪り、愚痴って、逆さまの苦しみの中に日々を送っております。人間の持つ悲しき業というのでしょうか。この業から解き放たれることのできるのがお盆なのです。
そして、いずれはご先祖の列に加わる私たちです。ですから、お盆はなつかしい心の故郷とも言えるのです。
宗教詩人 坂村真民さんの「お盆」という詩を読ませていただきます。
亡くなった人たちに会える日をつくって下さった
釈迦牟尼世尊に 心からお礼を中し上げよう
そして亡くなった人たちが 喜んで来て下さる 楽しいお盆にしよう
せっかく来て下さった方々を 悲しませたり 落胆させたり
もう来ないことにしようなど 思わせたりしない
心あたたかいお盆にしよう
迎え火のうれしさ 送り火のさびしさ
そうゆう人間、本然の心にかえって
守られて生きる ありがたさを知ろう
と、念唱されました。
お盆には、ご先祖を思い、亡くなった人たちをしのびながら、ご縁ある我が身を実感し。
お陰さまの心、供養の心をもって、餓鬼道に堕ちぬ自分を作ってゆきましょう。
ご先祖様はそうした子孫を見守ってくださることでありましょう。
このたび、当布教師会より法然上人800回大遠忌記念事業として法話集「法然さまからのお手紙とお歌」を出版いたしました。
法然さまが「黒田の聖人(ひじり)」に宛てた一紙小消息を、管長猊下お手ずから、わかりやすく現代の言葉に置き換えていただき、それを一区切りづつ布教師会の布教師がお説教として書き下ろしました。 また法然さまの代表的なお歌を八首取り上げ、それをテーマとしたお説教も掲載しております。
この本のお求めは、≪総本山誓願寺公式サイト「出版書籍のご案内」ページ≫ よりご購入いただけます。(一部1,000円税込/送料別)
facebook area